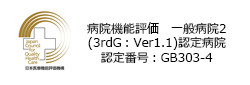判定基準
A:精神状態
| (1)知的機能 |
MMSで評価 ○/30で点数を表していく。MMS不可の場合、微細判定 。 |
| (2)精神症状 |
(1)思考迂遠 (2)幻覚 (3)妄想 (4)感情鈍麻 (5)抑鬱 (6)興奮 (7)意欲低下 (8)多幸 (9)不安 当てはまる番号をチェックし程度を記入
程度は (+)軽度、(++)中等度、(+++)重度で示してください |
| (3)行動症状 |
(1)徘徊 (2)夜間不穏 (3)独語 (4)離院 (5)暴力行為 (6)叫声 (7)常同行為
|
B:身体機能
| (1)ROM |
(1)頸部 (2)体幹 (3)右上肢 (4)右下肢 (5)左上肢 (6)左下肢
※制限が著明な部位もしくは問題となっている部位の番号を書き、どの関節のどの部位に制限があるのか。もしくはどういった状態なのかを簡単に明記し、計測の角度を記入する。 |
| (2)筋力低下 |
(1)頸部 (2)体幹 (3)右上肢 (4)右下肢 (5)左上肢 (6)左下肢
※筋力低下が著名な部位もしくは問題となっている部位を○/5で記入 |
| (3)感覚 |
(1)深部 (2)表在
※番号と低下部位と程度を記入 |
| (4)体幹機能 |
- 0=まったく寝たきり
- 1=ギャッジアップ可。枕などの固定の必要性(+)
- 2=ギャッジアップ可。枕などの固定の必要性(-)
- 3=車椅子坐位は可能。耐久性なく短時間で姿勢が崩れる。
- 4=車椅子坐位は可能。耐久性はあるが姿勢が崩れるため、抑制帯等の必要性(+)
- 5=車椅子坐位は可能。耐久性はあり抑制帯等の必要性(-)
- 6=トランスファーが可能で通常の椅子にも座れる。
- 7=椅子からの立ち上がりが可能。手すり(+)
- 8=椅子からの立ち上がりが可能。手すり(-)
- 9=立位保持が可能であるが、不安定である。
- 10=安定している。正常である。
|
C:日常生活動作
(1)食事:ムセがある場合は、番号のチェック後、空欄に程度(+、++、+++)を記入
| (嚥下機能・形態) |
- 0=IVH
- 1=経鼻栄養、胃瘻よりの経管栄養
- 2=経口摂取可:流動食
- 3=経口摂取可:ミキサー食
- 4=経口摂取可:半固形
- 5=全粥
|
- 6=再炊
- 7=米飯(常食)が可
- 8=めん類まで可
- 9=パンまで可
- 10=Anything OK
|
| (食事動作) |
- 0=食事形態0または1
- 1=何らかの形(らくらくゴックン等)で経口摂取が可能。
- 2=全介助を要する。(スプーンによる)
- 3=食事介助を要する。
- 4=スプーン以外の補助具を要する。
- 5=辛うじてスプーンで可
- 6=スプーンで食べこぼしがあるが半量以上自力にて摂取可。
- 7=通常のスプーンなら十分に可。
- 8=箸にて食べこぼしが目立つ。
- 9=箸にて食べこぼしがある。
- 10=正常。
|
| (2)移乗動作 |
- 0=不能、全介助(車椅子からベッド)
- 2=介助者一人でかなり引き上げ、体を回してもらう必要がある。
- 4=軽く引き上げてもらい移乗する。ヒポットの際に支えてもらう。
- 6=バランスを崩さないように手をそえてもらう程度の介助が必要。
- 8=車椅子を手すり代わりに使用して移乗しているが、監視が必要。
- 10=自立
|
| (3)整容動作 |
- 0=全介助(洗面、整髪、歯磨き、ひげ剃り)
- 2=類似動作はできるが、かなりの介助が必要。
- 4=動作はできるが、仕上げ等少しの介助が必要。
- 6=準備し指示すれば出来る。
- 8=要指示で可能。
- 10=自立(引き出しからの出納も含めて道具の操作・管理が出来る)
|
| (4)トイレ動作 |
- 0=全介助または不可能(おむつの使用)
- 1=おむつ交換の際にお尻を上げたり、横向きになれる。
- 2=ポータブルトイレで監視及び部分介助を要する。
- 3=日中はポータブルトイレを使用し夜間はおむつを使用する。
- 4=トイレで可能であるが監視・誘導・声かけを要す。(洋式・和式・ポータブルは問わない)
- 5=ポータブルトイレで自立。
- 6=手すりがあれば洋式で可能。
- 7=洋式であれば可能
- 8=手すりがあれば和式でも可能。
- 9=手すりがなくても可能であるが、やや不安定である。
- 10=自立(洋式・和式・手すりの有無に関わらず可能)
|
| (5)歩行 |
- 0=不可。
- 1=平行棒内。介助(+)
- 2=平行棒内。介助(-)
- 3=歩行器、手すり等を使用し、要介助。車椅子の必要性(+)
- 4=歩行器、手すり等を使用し、要監視。車椅子の必要性(-)
- 5=歩行器、手すり等を使用し、自立。しかし、活動範囲は制限。
- 6=平地歩行可能。
- 7=平地歩行可能。応用歩行(坂道や砂利道)困難。
- 8=応用歩行可能。監視及び介助の必要性(+)
- 9=応用歩行可能。監視及び介助の必要性(-)スピードや耐久性↓
- 10=正常。(補装具の使用は問わない)
|
| (6)車椅子駆動 |
- 0=不可
- 2=走行のみ可能。(速さは問わない)
- 4=移乗やバック等、細かい操作に介助を要する。
- 6=時に指示が必要(ブレーキ及びフットレスト、細かい動作)
- 8=駆動可能であるが完全に自立していない。
- 10=自立。
|
| (7)更衣動作 |
- 0=全介助(靴、ボタンかけ、装具の着脱も含む)
- 2=かなりの介助を要する。
- 4=介助を要するが、作業の半分以上は自分で行える。
- 6=着脱はできるが、ボタンかけ等の細かい動作ができない。
- 8=要指示で可能。
- 10=自立。
|
D:その他
| (1)排便 |
- 1=浣腸、薬物等あらゆる治療が必要。
- 2=緩下剤服用にて排便あるも時に浣腸も必要。
- 3=緩下剤服用にて排便が得られる。
- 4=自然排便あるも時に緩下剤の服用を必要とする。
- 5=自然排便
※コメントとして、下痢なのか便秘なのか、排便の障害も記入。 |
| (2)排尿 |
- 1=留置カテーテル及び残尿が多く導尿が必要。
- 2=尿意がなく、常に尿失禁状態。
- 3=尿失禁状態であるが、時に尿意を訴える。
- 4=時に尿失禁がみられたり、頻尿などの排尿障害がある。
- 5=正常
※コメントとして、頻尿、夜間頻尿等の排尿障害の内容も記入。 |
| (3)言語 |
(1)運動性 (2)感覚性 (3)構音障害
番号と程度を記入する。
(+)話は伝わるものの聞き取りにくい、または、わかりにくい。
(++)イエス/ノー等の簡単な意思表示は可能。
(+++)まったく話が伝わらない。 |
※特記事項としては、その患者特有の問題点を。例えば疼痛や家族との関わり等自由に記入する。
※評価は原則として腹臥位療法開始より1週目、2週目、4週目、2ヶ月目、3ヶ月目に提出するのが望ましく、後は変化が見られた時点で提出。例えば、リハを何らかの原因で中断した場合、開始時評価を行う。その際は、評価表上部の空欄に「リハ再開」と記入する。
評価表
腹臥位療法実施患者 経過および評価表[PDFファイル/9KB]
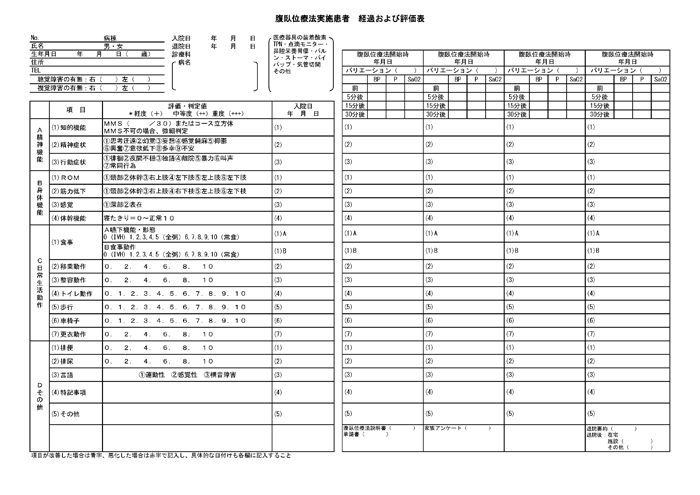
 <外部リンク>
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

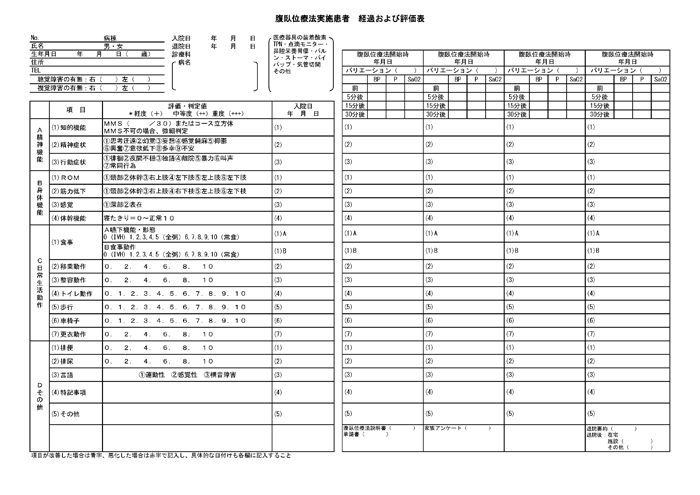
 外来診療のご案内
外来診療のご案内 活動・取り組み
活動・取り組み 地域医療連携
地域医療連携 研修医募集
研修医募集 採用情報
採用情報