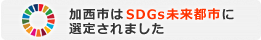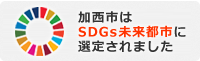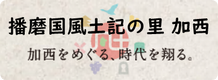本文
養育費と親子交流(面会交流)について
こどもの健やかな成長のために
こどもにとって、両親の離婚はとても大きなできごとです。
こどもがそれを乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚をするときに親としてあらかじめ話し合っておくべきことに、「養育費」と「親子交流(面会交流)」があります。
養育費とは
養育費とは、こどもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費などです。親の養育費支払義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障しなければならない強い義務、生活保持義務であるとされています。
養育費は、父母が離婚する前に話し合って具体的に取り決めておくことが大切です。離婚する際に取り決めることができなかった場合、こどもを監護養育している親は、離婚後、こどもが自立するまでは、こどもと離れて暮らしている親に対していつでも養育費を請求することができます。取り決めの内容は、後日その内容について紛争が生じないように、公正証書にしておくことをお勧めします。
養育費全般については下記ホームページで案内されています。
裁判所
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/youikuhi-tetsuzuki/index.html<外部リンク>
加西市では、養育費確保のための支援事業を行っています。
https://www.city.kasai.hyogo.jp/site/kosodate/1540.html
親子交流(面会交流)とは
親子交流(面会交流)とは、こどもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが、こどもと定期的または継続的に会って話をしたり一緒に遊んだりして交流することです。たとえ両親が離婚しても、こどもは父母のどちらからも愛されていると実感できることによって深い安心感と自尊心を育むことができます。
なお、離婚(別居)前に家庭内で暴力があった場合などで、相手方からDV被害を受ける恐れがあるなど、親子交流をすることがこどもの最善の利益に反する場合にまで親子交流を行う必要はありません。
法務省 親子交流(面会交流)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00017.html<外部リンク>
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(民法等改正)
父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。
2024年(令和6年)5月に民法等改正法が成立し、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責任を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直されました。
この法律は、2026年(令和8年)5月までに施行される予定です。
詳細については、法務省ホームページをご確認ください
<参考>
(法務省)民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html<外部リンク>
(法務省)パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)
https://www.moj.go.jp/content/001449160.pdf<外部リンク>
養育費関連の動画など
裁判所「離婚をめぐる争いから子どもを守るために」
https://www.courts.go.jp/saiban/video/kodomo_video/index.html<外部リンク>
Youtube法務省チャンネル 「リコンの時に知っておきたい大切なこと」
https://www.youtube.com/watch?v=Md4xNsuYbME<外部リンク>
YouTube法務省チャンネル 養育費バーチャルガイダンス2021
https://www.youtube.com/watch?v=U_dztFlDhaw<外部リンク>
法務省「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」
https://www.moj.go.jp/content/001322060.pdf<外部リンク>