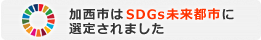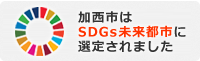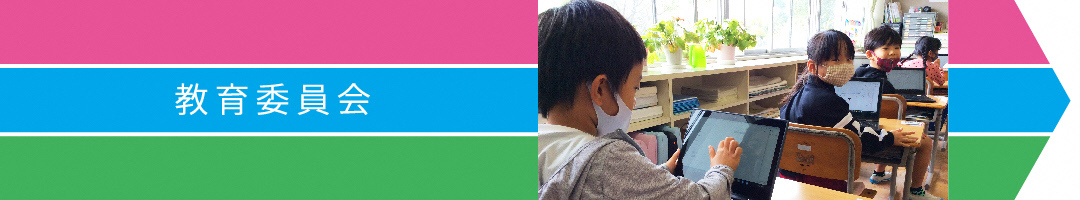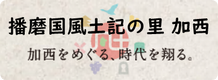本文
リーディングスキルトレーニング
加西市では、子どもたちの学力向上はもちろん、将来にわたって社会を生き抜く力を身につけるために、すべての小中学校で「リーディングスキルトレーニング」を開始します。
リーディングスキルトレーニングって何?
リーディングスキルは、「教科書を自力で正確に読める力」と考えてください。これをトレーニングするために開発されたのがリーディングスキルトレーニングです。開発者の新井紀子さんは日本におけるAI研究の第一人者です。子どもたちにAIに負けない読解力を身につけてほしいという願いから考えられました。これを実践している福島県相馬市では飛躍的に学力が向上しています。
リーディングスキルを体験しましょう
次の問題を考えてみてください。
Q 次の文を読みなさい。(新井紀子著「シン読解力」東洋経済新報社より)
幕府は、1639年、ポルトガル人を追放し、大名には沿岸の警備を命じた。
上記の文が表す内容と以下の文が表す内容は同じか。「同じである」「異なる」のうちから答えなさい。
1639年、ポルトガル人は追放され、幕府は大名から沿岸の警備を命じられた。
正解は「異なる」です。でも、中学生でこの問題に正解した生徒は57%しかありませんでした。新井さんは、著書の「シン読解力」の中で、こんな「誰でもわかるはず」の文章が読めていないことが衝撃的だったと述べられています。
次の問題はどうでしょう。考えてみてください。
Q 次の文を読みなさい。(新井紀子著「シン読解力」東洋経済新報社より)
(整数のうち)2で割り切れる数を偶数という、そうでない数を奇数という。偶数をすべて選びなさい。
(1)8 (2)110 (3)65 (4)0
正解は(1)(2)(4)です。「0って偶数なの?」と驚かれる方もいると思いますが、「0÷2=0 余り0」ですので、0は2で割り切れるので偶数となります。『割り切れる=余りが0のとき』という知識があれば、他の知識は必要ありません。問題や定義を正確に読み取って解答する力が問われます。「0は何もないから割れない」といった日常的な感覚はここでは邪魔になります。
リーディングスキルトレーニングの2つの柱
1.教科書を自分で読めるようになるトレーニング
教科書で使われている言葉は、私たちがふだん使っているものとは異なります。これを学習言語と呼びます。上記のような問題やリーディングスキルを意識した授業を通して、学習言語の理解を深めます。(学習言語の理解)
2.学習がスムーズにできるようになるトレーニング
指示された教科書のページを素早く開けたり、黒板に書かれた内容を素早くノートに視写できるようにすることで、認知的な負荷を軽減し学習に集中できるようにします。トレーニングではノートと鉛筆を使いこなすことが大切な要素になります。(認知的な負荷の軽減)
リーディングスキルトレーニングの実施
リーディングスキルトレーニングの実施場面は、主に以下の3つです。
- 学校でのトレーニング(週2~3回 1回10分程度)
- 教員によるリーディングスキルを意識した授業 (全教科)
- 家庭でのトレーニング (子どもの自主的なトレーニング)
- 1と2は学校で行います。
- 3は家庭で子どもたちが自主的に行います。
- 小5以上の児童・生徒は、RSTの個票のアドバイスに基づいて行います。
- 小4以下の児童については各学校の実情に応じて実施します。
- 保護者の皆さんにはお子様が自主的に意欲をもって取組めるよう見守り、励ましていただければと思います。可能であれば一緒にトレーニングを楽しんでいただければさらに大きな成果が期待できると考えております。
リーディングスキルトレーニングによって獲得した読解力は消えることはありません。この力は、学力の向上はもちろん、子どもたちが将来、社会で生きていくときの揺るぎない基盤になります。そのためにも、学校と家庭が一丸となって取り組み、最高の成果を追求していきたいと考えております。