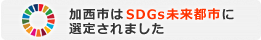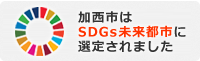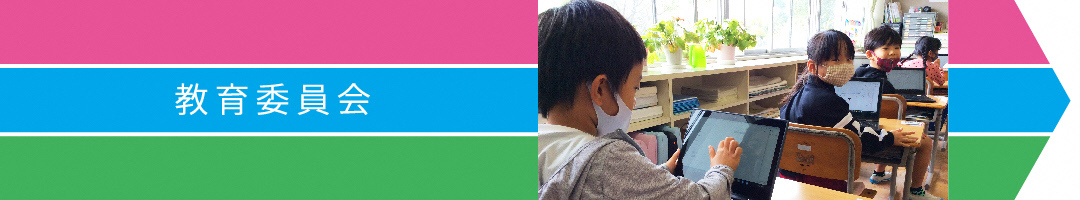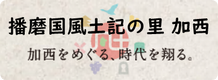本文
2025 加西STEAM ホワイトペーパー
加西市教育委員会は、「加西の教育3本の矢」(加西BASE、加西STEAM、加西GLOBAL)を中心に教育活動を展開しています。「加西STEAMホワイトペーパー」は、その3本の矢のうち「加西STEAM」に焦点を当て、その背景、目標、具体的な取り組み、および関連する重要な要素をまとめたものです。また、教職員であるユーザーの視点に立ち、指針や情報を提供し、ユーザーの課題解決に向けた推進の手助けとなることを目的としています。
「3C 次世代型人材」の育成
加西市は、「郷土を愛し 豊かに 未来を拓く 人づくり」を教育の基本理念としています。この理念に基づき、20年後の「未来の大人づくり」を目指し、「3C 次世代型人材」を育成する新しい教育ビジョンを掲げました。「3C 次世代型人材」とは、加西STEAMを通して育成を目指す人物像であり、以下の 3つの資質・能力を備えています。
- 挑戦(Challenge): 正解のない問題に挑む力
- 協働(Collaborate): 多様な他者と協働する力
- 創造(Create): 新しい価値を創造する力
これらの能力は、子どもたちが Society 5.0 や SDGs、VUCA 時代といった社会の変化に 対応し、Well-Being な生活を送るために、きっと役立つものと位置づけています。
加西STEAMの概念と特徴
加西STEAM は、STEM(科学、技術、工学、数学)教育に Arts(芸術/文系)の要素を 加えた STEAM 教育を通して、「3C 次世代型人材」を育成する新しい教育ビジョンです。 その特徴として、以下の点が挙げられます。
- 探究心と創造性の重視 ホンモノに触れ、「なぜ?」「知りたい!」「創りたい!」といった探究心を刺激し、正解 のない問題に挑戦し、多様な他者と協働し、新しい価値を創造する力を育むことを目指 します。
- 「探究し知る学び」と「発想し創る学び」のサイクル ICT を活用しながら、この2つの学びのサイクルを回すことを推奨しています。これは、兵庫教育大学の知見に基づき、スタンフォード大学のデザイン思考の 5ステップを取り入れたものです。
- ユーザー設定の重視 教材開発のスタートにあたり、「ユーザー(何かに困っている人)」は誰なのか、ユーザ ーの困りごとに子どもたちが「共感」できるのかを意識します。
- 多様なステークホルダーとの連携 学校だけの自前主義に陥らず、行政機関、企業、大学、NPOなど様々なステークホルダーと連携し、総合的な学習時間を中心に、学校行事や特別活動など、あらゆる教育活動の場面で新たな学びを展開しています。
加西STEAMの実践 3本柱とロードマップ
加西市は、「加西 STEAM 宣言」(令和3年度)、「サードプレイス宣言」(令和4年度)を経て、「加西 STEAM Vision Book」に基づきSTEAMの実装とSTEAMプログラムを実施しています。
柱1:総合的な学習の時間×STEAM
「ワクワク感のある学び」をコンセプトに、既存の実践のリメイク、加西市の魅力的な リソースとの連携、教科横断的な教材開発を行います。加西市はふるさと納税額が全国 上位と多くの方々から応援を受けており、地域には魅力的な「リソース」が数多く存在します。
柱2:GIGA × プログラミング教育×STEAM
「学びのDX化」をコンセプトに、プログラミング的思考の育成を重視し、プログラミングキットの整備(加西KOOVキット貸出)、ICT 支援員による授業支援、大学連携 によるカリキュラム支援・教職員研修・効果検証などを行います。
柱3:特別活動・学校行事×STEAM
「Well-being よりよい生活へ」をコンセプトに、既存の学校行事や特別活動にユーザー を設定し、よりよい学校生活への提案を行う実践を行います(例:掃除×STEAM、防災×STEAM、学校フェス×STEAM)。
令和3年から7年を見据え、e-ラーニング、STEAMフェス、Vision Book作成、カリキュラム実装、STEAMプログラム開発、プラットフォーム構築、White Paper作成、教職員研修、STEAM担当者設置など、段階的な施策展開を示しています。
2つの「学びのサイクル」
加西STEAMは、「探究し知る学び」と「発想し創る学び」の2つの学びを重視し、これらを往還する学びを推奨しています。 これまでの総合的な学習の時間に行ってきた探究的な学びに加え、ユーザー設定、共感、問題定義、発想、プロトタイプ、テストといったデザイン思考の要素を取り入れつつ、探究 的な学習者の育成を目指します。2つのサイクルを意識的に組み合わせることで、「ワクワク感」のある教材開発と学習活 動の実現を目指します。
STEAM Labo. の整備と活用
令和4年度には、デジタル田園都市国家構想推進交付金を活用し、市内の全学校や公民館 など 21箇所に「STEAM Labo.」を新設しました。 STEAM Labo.は「新たな学び」を提供するためのスペースであり、「価値を創造する『ス ペース』」「他者と繋がる『オンライン』」「360度カメラで『リフレクション』」の3つのコンセプトを組み合わせています。様々なデジタルツールとアナログツールが配置され、他の学校や学校外のリソースとSTEAM教育を融合させることで、「新たな学び」の創出を期待するものです。
STEAM 研修と担当者の設置
加西市は、計画的な STEAM 研修を積極的に行っています。令和3年度は全教職員が STEAM教育を理解するための e-ラーニング、令和4年度からは実践的な STEAM研修を実施しています。すべての学校にSTEAM担当者やSTEAM教育推進委員会を設置し、STEAM教育への取り組みを強化しています。STEAM担当者は、兵庫教育大学での研修などを通して、最新のテクノロジーを活用しつつ、各学校で加西STEAMを推進する役割を担っています。
STEAMプログラムの拡充
STEAMプログラムは、通常の学校教育の枠を超えた分野やSTEAM特有の思考方法を 育む教育プログラムです。各学校の教育課程をベースにスポット的に導入されており、令和6年度からはプログラム数を拡充し、希望校へ提供しています。加西STEAMのステークホルダーとの連携を深め、多様な分野のSTEAMプログラムをコーディネートしていきます。
ステークホルダーとの連携
加西STEAMを実践的な学習体験へと高めるために、学校だけのリソースでは不十分であるという認識のもと、行政機関、企業、大学、NPOなど多様なステークホルダー(加西STEAM応援団)と積極的に連携しています。これらの連携を通じて、教材開発や学校支援、STEAM環境の整備を進めています。兵庫教育大学とのSTEAM連携協定をはじめ、文部科学省、兵庫県新産業課、企業、大学など多岐にわたる機関と連携しています。
サードプレイスの活用と情報発信
学校や家庭以外の「第3の場所」であるサードプレイスを、子どもたちの「あったらいいな」を具現化するスペースとして提供しています。図書館や公民館のSTEAM Labo.を活用したSTEAMプログラムの実施などを通して、「3C」が芽生える場を提供し、学校でのSTEAMの種を地域と共に育てることを目指しています。 毎年「加西STEAM Fes. in KASAI」を開催し、STEAM教育の魅力を発信しています。加西STEAMに関する情報は、専用HPや広報誌、教職員向けの通信などを通して積極的に発信し、理解と協力を広げています。
教員の負担軽減策
加西市教育委員会は、教員の負担軽減策にも取り組んでいます。スクール・サポート・スタッフ(SA)、学校業務支援員(GO)、部活動補助員などを配置し、教員の業務効率化と負担軽減を図っています。令和7年度からは、AI支援ツールを導入し活用することで、日常業務、計画書立案、報告書作成、指導案作成、生徒指導関係支援、会議録作成等、教師の業務負担の軽減を図ります。
おわりに
加西市教育委員会は、「3C次世代型人材」の育成を目指し、「加西STEAM」を核とした先進的な教育を推進しています。探究心と創造性を育むSTEAM教育を、総合的な学習時間、プログラミング教育、特別活動・学校行事の3本柱を中心に展開し、STEAM Labo.の整備、教員研修の充実、多様なステークホルダーとの連携、サードプレイスの活用などを通して、その実現を図っていきます。