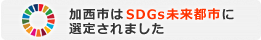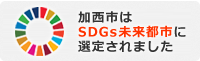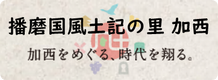本文
県指定文化財 奥山寺

多宝塔

本堂

地蔵院庫裏(手前)・客殿(奥)

仁王門
| 名称 | おくさんじ 奥山寺 |
|---|---|
| 種別 | 建造物 |
| 指定日 | 平成12年5月2日(多宝塔指定) 令和5年3月17日(11棟追加指定) |
| 員数 | 1基11棟 |
| 時代 |
多宝塔 宝永6年(1709) |
| 所在地 | 国正町 |
| 特徴 | 奥山寺は、白雉2年(651)、法道仙人による創建と伝わる古刹です。北は現・西脇市に、東は現・加東市に接しており、古くから広く崇敬を集めている本寺は、慶長6年(1601)に火災にあったのち、慶長12年(1607)に再興、その後、貞享4年(1687)に本堂をはじめとする諸堂を修理後、建て替えや改修などを経て今に至ります。 県指定重要有形文化財の建造物のうち、最も古い建造物は貞享4年(1687)に建設された本堂(大工:神田作左衛門)です。構造体として組み込まれた軒先の柱、蝙蝠様の花肘木、位置によって使い分けられた虹梁絵様などに地元の宮大工・神田氏の技術が発揮されています。式台玄関とその奥に池を備えた地蔵院客殿・庫裏は高野山金剛三昧院のそれに共通する要素でもあり、太子堂四足門・土蔵などを残すその姿は江戸期の格の高い子院の特徴をそなえています。現存する建物は江戸期以降のものですが、山の下にある楼門から小高い位置にある多宝塔まで、地形を活かした当寺の伽藍配置は、中世の山林寺院の在り方を今に伝える建造物群です。 |
※各ページに掲載の写真・画像及び記事等の無断転載を禁じます。